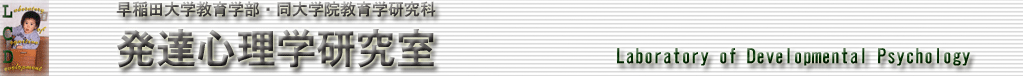Information
The 3rd London Reasoning Workshopに参加してきました。(from 中垣教授)
|
2008年8月18、19日にロンドンで第3回 London Reasoning Workshop があり、参加してきました。
London Reasoning Workshopはロンドン大学のMike Oaksfordがホストとなって、毎年夏休みに
彼の所属するBirkbeck Universityにおいて開催されているワークショップです。学会というほど
規模は大きくなく、イギリスを中心にヨーロッパの推論研究者30名ほどが参加する研究発表会と
いったところです。2006年より始まったので、今回が3回目ということになります。もっとも
これ以前からJonathan Evansらが中心になってこの種のワークショップを不定期に開催して
いたようです。何しろイギリスは4枚カード問題とかThog課題のような有名な(famousという
よりnotoriousというべき)推論課題を考案したPeter Wasonが活躍した国ですから、その関係で
演繹的推論研究はイギリス心理学における得意分野の一つとなっています。
私は2007年度特別研究期間をとってイギリスに滞在したとき、初めて参加したので、今回は 2回目の参加ということになります。今回私がこのワークショップに参加したときは、神戸 女学院大学の山祐嗣さんがちょうど特別研究期間をとってイギリスに滞在しているときでした。 しかもMike Oaksfordのところで研究生活を送っていたので、今回のワークショップ参加に 際しては色々とお世話になりました。山祐嗣さんは初回から参加している唯一の日本人で あるかと思います。 わたしは初参加の第2回 London Reasoning Workshopでは“Is domain-specific reasoning in conditional reasoning tasks really domain-specific?”というタイトルで研究発表 しました。これは4枚カード問題に代表される論理的推論課題における主題化効果が、 一般にそう信じられている領域特殊な推論様式(例えば、Cheng & Hollyoak 1985の 「実用的推論スキーマ」など)による効果ではなく、領域普遍的な命題的推論様式の 一つの現れであることを示そうとしたものです。それに対して、 今回2回目の参加で ある第3回 London Reasoning Workshopでは“Matching heuristic cannot explain matching bias in conditional reasoning.”というタイトルで発表してきました。 前回は4枚カード問題における主題化効果の既成の説明を批判する研究発表でしたが、 今回はそれを受けて主題化されざる抽象的4枚カード問題における特徴的効果である マッチングバイアスの既成の説明を批判する研究発表をしました。よく知られている ようにマッチングバイアスは抽象的4枚カード問題に特徴的に見られるバイアスであり、 命題論理学に従う規範的カード選択から大きく逸脱したこのバイアスの存在こそ 4枚カード問題をかくも有名な課題としたものです。マッチングバイアスの発見者で あるEvans(1972)は、マッチングバイアスをMatching heuristic(Evans et al., 1999) によって説明しています。Matching heuristicというのは「否定の有無に関わらず、 与えられたルールの中で明示的に言及されている事例に選択的に注意を向ける ヒューリスティック」(Evans et al., 1999, p.188)で、人は命題論理に従うよりも このヒューリスティックに頼るために4枚カード問題においてマッチングバイアスを 犯すと説明しています。では、マッチングバイアスとは何でしょうか。マッチング バイアスとは「4枚カード問題において、否定の有無に関わらず、与えられたルールの 中で明示的に言及されている事例を選択する傾向」です。両者の違いは一体どこに あるのでしょう。4枚カード問題では通常「p(でない)ならば、qである(でない)」と いう形式の条件文がルールとして与えられるので、Matching heuristicは「pと qに注目する便法」であり、Matching biasは「pとqを選択する傾向」となります。 では、「前者の便法があるから後者の傾向が生ずるのだ」というのは説明として 成立しているのでしょうか。今回の研究発表は、こうした説明はトートロジーであり、 説明としての体裁をなしていないことを論証しようとしたものです。 このようなテーマをLondon Reasoning Workshopでの発表テーマとして選んだのは、 説明としての体裁をなしているとは思われないMatching heuristicによるEvansの 説明を正面から批判する者が英米の研究者には誰もいないことです。先ほど指摘 したようにイギリスは演繹的推論研究の本場であるにもかかわらず、そして、 マッチングバイアスの発見以来35年以上経過しているにもかかわらず、マッチング バイアスの説明そのものは発見当初の説明とほとんど変わってないという事情が あったからです。英米の研究者は、「説明が変わっていない」ということは「進歩 がない」ということではなく、「説明が正しい」ことの傍証だと受け取っているの かもしれません。あるいは、Evansは現代における演繹的推論研究を代表する研究者 ですから、その考えを正面から批判するなどということは、英米の研究者には恐れ 多くてとてもできないのかもしれません。 本当の事情は図りかねますが、「英米の研究者が批判しないなら、私がやらざる をえないか」といういわば義侠心的な気持ちでLondon Reasoning Workshopに 乗り込んだことは確かです。今回のLondon Reasoning Workshopに参加しようと 思ったもう一つの事情は、Workshop の副題がFestschrift for Jonathan Evans to honour his 60th Birthdayとなっていることから分かるように、Evansの 60歳誕生記念研究発表会でもあったからです。別に「Evansの60歳をお祝い したいので、参加しよう」と考えたわけではありません。そうではなく、 「60歳を祝う研究発表会であるからには必ずEvansが参加するであろう」と 考えたからです(第2回 London Reasoning Workshopでは、Evansも参加して いることを期待して臨んだのですが、残念ながら参加していませんでした。 ほぼ同じ時期にイギリス発達心理学会がthe University of Plymouthであり、 Evansはこの大学の認知心理学教授を務めている関係でLondon Reasoning Workshopには参加できなかったようです)。Evansの考えを批判するからには Evansが臨席しているところでやり、Evans自身の反論を知りたかったからです。 Workshopでは討論時間も含めて1人35分の発表時間を与えられているので、 大きな学会のPaper Sessionにおける20分程度の発表より時間的余裕があります。 それだけに、Evans の面前で当事者の理論の鍵となるアイデアを批判することは、 こちら側に批判を根拠づける十分な証拠と彼のHeuristic-analytic Theoryに 代わる新しい理論を持ち合わせているとはいえ、さすがに緊張しました。 発表の最初に「4枚カード問題におけるマッチングバイアスは心理学的に既に 説明されたと信じているか。信じている人は手を上げてください」という 質問を会場の参加者にしました。すると3人の手が挙がりました。1人は 言うまでもなくJonathan Evansで、もう1人はこのWorkshopのホストMike Oaksfordです(もう1人いたかと思いますが、誰か覚えていません)。 ということは、会場にいた大部分の人はマッチングバイアスを心理学的 説明が与えられた現象だとは信じていないということでしょう。勿論、 手を上げなかったからといって、「心理学的説明が与えられた現象だとは 信じていない」と決め付けるわけにはいきませんが、Evansのいる前でも 手を上げないのですから、少なくともその可能性を示唆しているといえる でしょう(ちなみに、Evans と共著を書いたり共同論文を発表している David Overも手を上げていなかったので、この点をあとで確かめたところ、 彼もまたMatching heuristicでマッチングバイアスが説明できるとは 思ってないとはっきり認めていました)。 私の発表は30分ほどで終わり、討論に入りましたが、司会役のOaksford が 最初に指名した討論者は当然のことながらEvansでした。予想通り、Evansの 反論は大変厳しいものでした。第1の批判は、私の挙げた反証例は極めて selective reading(日本語で、「偏った文献レヴュー」とでも訳すべき なのでしょうか)で、Matching heuristicを支持するデータもたくさんある という反論でした。第2の批判は、マッチングバイアスの位置づけは最近の 自分の理論では変わっているのに、私の批判は少し前の自分の理論をターゲットに しているというものでした。Evansの反論は形式的にはどちらも認めますが、 実質的にはどちらも認めることができません。第1の批判については、 私のpresentationではEvansの説明を批判しているわけですから、それに 対して明確に反証例といえるものを選択的に挙げるのは当然のことです。 Matching heuristicでも他の考え方でも説明できるものを批判の根拠と して上げても無駄に終わるだけです。ここで、本来Evansがやるべき反 批判は私が反証例としてあげた根拠をつぶすことであって(例えば、 「あなたが挙げた反証例は実は反証例ではなくて、見方を変えれば むしろ検証例なのだ」という類の反論)、「Matching heuristicを 支持するデータもたくさんある」というのでは反批判になりません。 第2の批判については、確かにEvansのHeuristic-analytic Theory(Evans 2006) ではヒューリスティックな過程とアナリティックな過程とを従来のように 峻別するのではなく、両者の相互作用を認めるようになり、データの説明 可能性の範囲拡げたことは確かですが、マッチングヒューリスティックに ついては、“The matching heuristic causes items named explicitly in the statement to be perceived as relevant. This would also favor A over D but also 3 over 7.”(Evans, 2006, p.388)と書いていることから 明らかのように、マッチングバイアスの説明については最近のEvansの理論に おいても全くといっていいほど変わっていないのです。ですから、マッチング ヒューリスティック批判に関しては、最近のHeuristic-analytic Theoryも 旧来の理論も区別する必要がないのです。Heuristic-analytic Theoryに 関していえば、最近の理論はむしろヒューリスティックな過程とアナリ ティックな過程との区別をあいまいにすることによって、両過程を区別する 必要性が不明瞭になり、理論的構成の明確さという観点からむしろ後退して いるといえるでしょう。いずれにせよ、今回の発表でEvansを説得できる などとは初めから考えていませんでしたが、少なくとも「マッチング バイアスは既に説明済みである」と考えてはならないことは多くの参加者に 理解してもらえたのではないかと思っています。この議論をより説得的に していくためには、Heuristic-analytic Theoryに代わる、マッチング バイアスの新しい説明理論を積極的に提示していくことが必要でしょう。 最後に、WorkshopはEvansの60歳誕生記念研究発表会でもあったわけですから、 勿論Evans自身のpresentationもありました。このプレゼンテーションは Evans自身の40年近くにわたる研究史と各年代における推論研究の研究動向を Evansの研究関心から要約したものでしたから、私自身にとっても大変興味 深いものでした。特に、プレゼンテーションのスライド3枚目で次のように 言っています。
第一に、Wasonが人の推論におけるバイアスと非合理性を示し、ピアジェの論理主義を 反駁することに情熱を持っていたことが紹介されている。このことは、推論における バイアスや非合理的反応はピアジェのアプローチでは説明できないものと捉えられて いることです。Wasonの教え子であるEvansは、ピアジェ理論についてそれを評価する だけの知識を持ち合わせていないようで、ピアジェ理論に言及することはほとんど ないので、Evans自身がどう捉えていたかは分かりませんが、師のWasonの捉え方を 踏襲しているとするのがもっとも自然でしょう。とすれば、演繹的推論における 代表的バイアスであるマッチングバイアスはピアジェ理論では説明できず、Matching heuristicに訴える必要があるとするEvansの説明に対して、マッチングバイアスは Matching heuristicでは説明できず、ピアジェ理論に訴える必要があるとする 今回の私のプレゼンテーションは、意趣返しのニュアンスがあるかもしれません。 もっとも、今回のプレゼンテーションではマッチングバイアスをどう説明すべきと いう点に力点があったのではなく、Matching heuristicはマッチングバイアスの 説明にはなっていないことを示すことが目的でしたので、Matching heuristicに 代わる新しい考え方があることに触れただけで、それを積極的に提示することはしていません。 第二に、1970年代当初から、演繹的推論についてWason & Evansがやっている研究と 確率的推論におけるKahneman & Tverskyの heuristics and biasesアプローチとの 間に並行的関係を見ていたことです。確率的推論におけるHeuristics and biases アプローチがKahneman & Tversky に代表されるとすれば、自分たち(Wason & Evans) が演繹的推論におけるheuristics and biasesアプローチを代表してきたという 自負が窺えます。Heuristics and biasesアプローチは演繹的推論や確率的推論の 研究において1970年以前に支配的であった古典的合理主義的アプローチに対する Alternativesとして提出され、現代でも支配的アプローチの一つであります。 しかし、1990年代になるとCosmides やGigerenzerに代表される進化論的・生態学的 アプローチも喧伝されるようになり、現代の演繹的推論・確率的推論研究における もう一つの大きな陣営を作っている。それに対して、われわれの研究室では、 確率理論や命題論理学を規範的理論として認めつつ、認知システムに固有の ダイナミズムによって推論バイアスを説明しようとする新しい理論を提唱している。 言い換えれば、古典的合理主義的アプローチとheuristics and biasesアプローチを 統合して、特殊な進化論的合理性や生態学的合理性を仮定することなく、人の 推論における規範性と逸脱性を同時に説明しようとする力動的合理主義的 アプローチである。このアプローチを実証的にも理論的にも堅固なものとして 確立していくことがわれわれの研究室における一つの重要課題となるであろう。 以下では、学会発表の様子を写真で紹介していますので、ご覧ください。 第2回 London Reasoning Workshop(2007年8月28-29日)で撮った写真も 混じっていますが、Workshopの様子は第3回のときと全く変わっていません。 
University of Londonの中の一つのカレッジBirkbeck Collegeの建物です。 London Reasoning Workshopは毎年この建物の中で行なわれています(2007年撮影) 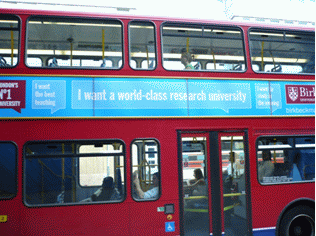
ロンドン名物二階建バスの車体にBirkbeck Collegeの広告を見つけました(2007年撮影)。 I want a world-class research university. と宣伝しているように、Birkbeck Collegeはロンドン大学の中でも世界的レベルの研究者養成を目指すカレッジである ことを自認しているようです。 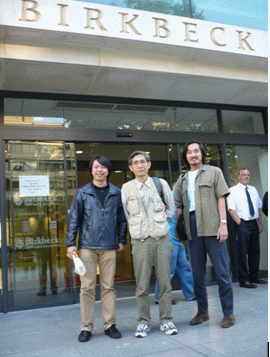
Birkbeck Collegeの入り口近くで撮った写真(2007年撮影)。私が初めてLRWに 参加したときのものです。右が神戸女学院大学の山祐嗣さん、左が神戸女学院 大学に研究滞在しているという中国人研究者です。 
私のプレゼンテーションの様子です。山さんに撮影してもらいました。 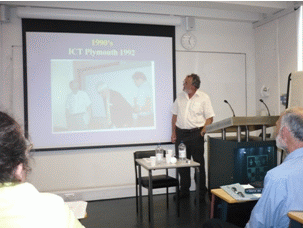
Evansのプレゼンテーションです。スライドに写っている3人の人物は左からPhilip Johnson-Laird、Peter Wason、Jonathan Evansです。イギリスPlymouthで開催された 第2回International Conference on Thinking(1992)のシンポでの1コマのようです。 
これは研究発表セッションの間に催されるTea & Coffeeタイムの1コマです(2007年撮影)。 手前テーブルに手を伸ばしているのがメンタルロジック派の代表的研究者David O’Brien、 その背後に写っている二人の研究者は、右がフランスのメンタルロジック派に近いGuy Politzer, 左後ろ向きに写っているのがEvansの共同研究者で来日したことのあるDavid Over、ポケットに手を入れて写真の奥に写っているのがホストでBayesian アプローチの Mike Oaskford、その左の男性が推論における論理的プロセスと解釈的プロセスを統合 しようとするKeith Stenning, その左でOaskfordと対面しているのがDeonticロジック 派のKen Manktelowである。 
会場近くのイタリアンレストランで行なわれた懇親会の様子 
London滞在中はKensington Gardenの南西に当たるEarl's Court Station近くの 安ホテルに宿泊しました。うらぶれた街角でしたが、ここからWorkshop会場に もっとも近いRussell Squareへも、出入国の基地となるHeathrow空港へも、 ロンドン中心部のPiccadilly CircusへもPiccadilly Line一本で行けたので、 大変便利なところでした。 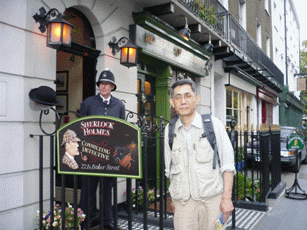
折角ロンドンまで来たので、コナン・ドイルの探偵小説の主人公シャーロック ホームズが住んでいたとされるBaker Street 221Bに行ってきました。今は 観光博物館になっています。 
Baker Streetから有名なマダムタッソーろう人形博物館を通ってReagent’s Park へ行ってきました。公園のあちこちでバラの花が咲いていましたが、季節は8月中 ごろのため、美しくはあるが、少し疲れた表情のバラでした。ロンドンでは7月 初めがバラの見ごろになるのではないでしょうか。 |
早稲田大学教育学部
早稲田大学大学院教育学研究科 中垣研究室
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1
TEL:03-5286-1598 E-mail:nakagaki@waseda.jp
*メール送信時は@を半角にしてください。
All rights reserved. (c)2009.