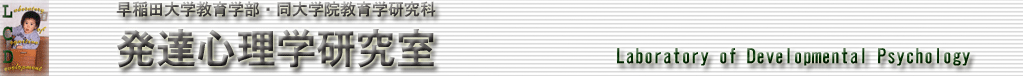三國 隆子
■出身大学■
日本女子大学
■趣味■
クラシックギター演奏
ピアノ演奏(ジャズに挑戦しています!)
■研究テーマ■
- 親族の論理的関係の理解が成立する過程と呼称にみる親族関係の構造について
- 保育者のワーク・ライフ・バランスについて
■研究内容■
- 子どもが親族関係をどのように理解していくのか。例えば、自分からみた姉=自分の母親からみた娘であるといった、親族の論理的関係を子どもは発達に応じてどのように理解していくのか。
また、呼称(呼び名)によって親族関係がどのように形成されるのか。例えば、子どものいる夫婦がお互いを「お父さん、お母さん」あるいは「パパ、ママ」と呼び合うことがあるが、子どもをもつことによって、このような子ども中心の呼称に変化することで、夫婦の関係性にも変化が生じるのか。
- 子どもを保育する保育者自身が子をもつ親となったとき、自分の子育てと保育の仕事をどのように捉えるのか。
■業績■
著書・テキスト
- (2008)「夫婦間の親族呼称」清水浩昭編『家族社会学へのいざない』岩田書院.
- (2007)「家庭との連携section4」七木田敦編『実践事例に基づく障害児保育』保育出版社.
論文
- (2007)保育者の労働形態選好と性役割観に関する研究の課題と展望.郡山女子大学紀要第43集
- (2006)子どもをもつ夫婦の呼び名の変化に関する一考察.郡山女子大学紀要第42集
阪脇 孝子
■出身大学■
京都大学
放送大学
■趣味■
読書、温泉めぐり
■研究テーマ■
順列課題を用いた社会的相互作用と認知発達、仮説演繹的思考の発達
■業績■
論文
- 阪脇孝子・中垣啓(2009) .順列操作の実行的理解と概念的理解:「対称性の理解」を中心に. 発達心理学研究, 20, 337-350.
- (2007). 認知発達水準と認知的変化の関係についての一考察 −順列課題を用いた社会的相互作用事例の検討−.早稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊15−1
- (2009).「科学的思考」についての一考察−Piagetの「形式的操作」の観点から−. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊, 16-2
- (2009).「知ること」の意味と「科学的思考」との関係 -Kuhnによるモデルの再検討-. 早稲田大学教育学会紀要, 10
- (2010). 大学生の仮説検証方略についての考察. 早稲田大学教育学会紀要, 11
- (2011). 「科学的思考」を問う課題における子どもの推論の特徴について―Piagetの発達理論からの説明の試み―. 学術研究. 教育心理学編, 59. 早稲田大学教育学部
学会発表(ポスター)
- 阪脇孝子・中垣啓 (2007). 順列実行方略一般化の発達について. 日本発達心理学会大会第18回論文集,630.埼玉大学.
- 阪脇孝子・中垣啓 (2007). 順列課題の概念的理解について―順列の総数予測課題からの考察―. 日本教育心理学会第49回大会論文集,320.文教大学.
- (2008). 順列課題の実行的理解と概念的理解の変化について. 日本発達心理学会第19回大会,283.追手門学院大学.
- (2008). The qualitative analysis of conceptual understanding of combinatorial problems during and after the peer interaction.XXIX International Congress of Psychology.Berlin,Germany.
- (2008). 順列の実行的理解に関する社会的相互作用の影響について. 日本教育心理学会第50回大会論文集,699.東京学芸大学.
- (2009). 社会的相互作用前後の順列実行的理解の変化要因の検討 ―順列の「きまり」に関する理解の観点から―. 日本発達心理学会第20回大会論文集, 617. 日本女子大学
- (2009). 仮説演繹的思考の発達に関する考察. 日本教育心理学会第51回総会発表論文集, 416. 静岡大学
- (2010). 実験場面における大学生の推論について. 日本発達心理学会第21回大会論文集, 関西エリア連合, 100. 神戸国際会議場, 兵庫.
- (2010). 仮説の生成・検証プロセスと命題操作の関係. 日本心理学会第74回大会発表論文集, 1061. 大阪大学.
- (2011). 組合せ操作の発達に関する考察―べき集合課題を用いて―. 日本発達心理学会第22回大会論文集, 643. 東京学芸大学.
学会発表(口頭)
- (2009).「知ること」の意味と「科学的思考」との関係 -Kuhnによるモデルの再検討-. 第10回早稲田教育学会. 早稲田大学
- (2010). 大学生の仮説検証方略についての考察. 第11回早稲田教育学会. 早稲田大学
- (2010). 仮説の生成と仮説検証方略に関する発達的検討. 日本教育心理学会第52回総会発表論文集, 688. 早稲田大学
学会発表(自主シンポジウム)
- (企画・司会)永盛善博,(話題提供)伊藤朋子・大浦賢治・柿原直美・阪脇孝子. (2010). 教職課程で発達心理学を学ぶのはなぜか?―認知発達の観点から子どもの発達と教育の関係を探る―. 日本教育心理学会第52回総会発表論文集, 210-211. 早稲田大学, 東京.
学会発表(ラウンドテーブル)
- (2008). 子どもが「本当に」できることは何なのか?−Piagetの「操作」から子どもの有能性を探る−. 企画者. 日本発達心理学会第19回大会発表論文集, 201. 追手門大学, 大阪.
- (2009). Piagetの認知発達理論を読み解く. 話題提供者. 日本発達心理学会第20回大会発表論文集, 76. 日本女子大学, 東京.
- (2010). Piagetの認知発達理論から子どもの学習のつまずきを考える. 話題提供者. 日本発達心理学会第21回大会発表論文集. 関西エリア連合, 神戸.
- (2011). 具体から抽象へ, 「今ここ」から可能性へ―Piagetの発達理論から小学校高学年以降の学習の難しさについて考える―. 企画・話題提供者. 日本発達心理学会第22回大会発表論文集, 67. 東京学芸大学, 東京.
学会分科会報告
- (2004). 認知発達理論分科会第14回例会報告.C. A. Nelson, M. Luciana (Eds.), Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience (Cognitive Neuroscience of Development). 第20章 Language Development in Children with Unilateral Brain Injury.
- (2006). 認知発達理論分科会第19回例会報告.A. J. Baroody & A. Dowker (Eds.), The development of arithmetic concepts and skills: The construction of adaptive expertise. 第1章 The Development of Adaptive Expertise and Flexibility: The Integration of Conceptual and Procedural Knowledge.
- (2007). 認知発達理論分科会第23回例会報告. E. Amsel and J.P. Byrnes (Eds.), Language, literacy, and cognitive development: The development and consequences of symbolic communication. 第2章 Developing a Socially Shared Symbolic System,
By Katherine Nelson & Lea Kessler Shaw
- (2008). 第27回認知発達理論分科会. Mareschal, D., Johnson, M. H., Sirois, S., Spratling, M. W., Thomas, M. S. C., & Westermann, G.(Eds), Neuroconstructivism: Vol.1 第4章 Embodiment: representations in context.
- (2010). 第31回認知発達理論分科会. Parker, S. T., Langer, J., and Milbrath, C. (Eds.). (2005). Biology and Knowledge revisited: From neurogenesis to psychogenesis. LEA. 第1章Piaget’s Legacy in Cognitive Constructivism, Niche Construction, and Phenotype Development and Evolution.
伊藤 朋子
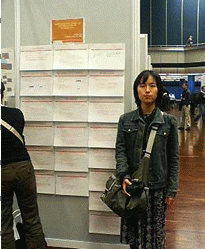 ■出身大学■
■出身大学■
早稲田大学
■趣味■
読書(直木賞作家の小説が好きです)
歩くこと(電車に乗らずに,東京の道をてくてくと歩くのが好きです)
■研究テーマ■
確率推論課題における推論様式の認知発達的研究
■研究内容■
幼稚園,小学校,中学校,大学などでの認知発達調査を通じて,確率観念がどのように発達してゆくのか,また,ベイズ型推論課題や連言錯誤課題などの確率推論課題における推論様式がどのように発達してゆくのか,などのテーマを明らかにしたいと考えております。
■業績■
修士論文
- (2007) 「サイコロ課題」における確率的推論様式の発達. 修士論文(未公刊). 早稲田大学. 東京.
論文
- (2008). 「ベイズ型くじびき課題」における推論様式の発達. 発達心理学研究, 19, 2-14.
- (2009). 確率量化操作の発達的研究:「サイコロ課題」を用いて. 発達心理学研究, 20, 251-263.
- (2010). 「ベイズ型くじびき課題」における推論様式の発達的分析:個数表記版・頻度表記版・割合表記版を用いて. 発達心理学研究, 21, 71-82.
- (2010). ベイズ確率論からの判断の逸脱−認知システムの働きに影響を及ぼす攪乱要因としてのフレーミング効果− [ショートノート]. 知能と情報(日本知能情報ファジィ学会誌), 22(4), 464-470.
- (2006). 確率的推論におけるバイアス(基準率の無視・連言錯誤)に関する先行諸研究の概観と今後の課題. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第13号(2), 早稲田大学, 東京, 1-11.
- (2006). ベイズ型推論課題における推論様式の分析−「予防接種問題」を用いて−. 早稲田大学教育学会紀要第7号, 早稲田大学, 東京, 89-96.
- (2006). 基準率の無視に関する現在の研究水準の概観と解明すべき課題. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第14号(1), 早稲田大学, 東京, 23-33.
- (2007). 「連言錯誤」に関する現在の研究の概観と解明すべき課題. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第14号(2), 早稲田大学, 東京, 1-11.
- (2007). 確率の1次的量化課題・2次的量化課題における推論様式の分析−「予防接種問題」を用いて−. 早稲田大学教育学会紀要第8号, 早稲田大学, 東京, 12-19.
- (2007). 確率観念の発達に関する先行研究の概観と今後の課題. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第15号(1), 早稲田大学, 東京, 195-205.
- (2008). 「ベイズ型」予防接種問題における推論様式の発達的分析−確率表記版と頻度表記版の比較−. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第15号(2), 早稲田大学, 東京, 131-142.
- (2008). 確率の定義に関する発達的研究. 早稲田大学教育学会紀要第9号, 早稲田大学, 東京, 9-15.
- (2008). 「ランダム系列の誤認知」に関する先行研究の概観と解明すべき課題. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第16号(1), 早稲田大学, 東京, 129-140.
- (2009). 「タクシー課題」「タクシー課題同型くじびき課題」における推論様式の発達的分析. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第16号(2), 早稲田大学, 東京, 137-148.
- (2009). 人は「確率」をどのようにとらえているのか. 早稲田大学教育学会紀要第10号, 早稲田大学, 東京, 15-19.
- (2009). ベイズ型推論に関する現在の研究の概観と今後の課題. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要(別冊)第17号(1), 早稲田大学, 東京, 157-168.
学会発表(ポスター)
- (2006). ベイズ型くじびき課題における推論様式の発達. 日本発達心理学会第17回大会発表論文集, 584. 九州大学, 福岡.
- (2006). ベイズ型予防接種問題における推論様式の発達−割合表記と頻度表記を用いて−. 日本教育心理学会第48回総会発表論文集, 299. 岡山大学, 岡山.
- (2007). 「条件付確率の質問形式をもつ1次的量化課題」における推論様式の分析. 日本発達心理学会第18回大会発表論文集, 408. 埼玉大学, 埼玉.
- (2007). 確率の「基本的な2次的量化比較課題」における推論様式の分析−「2段階くじびき課題」を用いて−. 日本教育心理学会第49回総会発表論文集, 435. 文教大学, 埼玉.
- (2007). 「1次的量化に還元可能な条件付確率課題」における推論様式の分析. 日本心理学会第71回大会発表論文集, 854. 東洋大学, 東京.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2007). 認知的浮動による連言錯誤の説明. 日本心理学会第71回大会発表論文集, 859. 東洋大学, 東京.
- (2008). 根元事象・和事象・積事象の起こりやすさの比較判断(質的量化)に関する発達的分析. 日本発達心理学会第19回大会発表論文集, 281. 追手門大学, 大阪.
- (2008). Developmental study on quantification of probability in the formal operational stage. Poster presented at the 38th annual meeting of the Jean Piaget Society, Quebec City, Canada.
- (2008). Developmental study on conservation of probability [Abstract]. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, 101. Berlin, Germany.
- (2008). ランダム系列の認知に関する発達的分析. 日本心理学会第72回大会発表論文集, 954. 北海道大学, 北海道.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2008). 認知的浮動による選言錯誤の説明. 日本心理学会第72回大会発表論文集, 931. 北海道大学, 北海道.
- (2008). 「ベイズ型くじびき課題」における推論様式の発達的分析−個数表記版・頻度表記版・割合表記版の比較−. 日本教育心理学会第50回総会発表論文集, 490. 東京学芸大学, 東京.
- (2009). 保存原理に関する発達的研究−確率の保存を対象に−. 日本発達心理学会第20回大会発表論文集, 618. 日本女子大学, 東京.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2009). 選言型推論における様相未分化の実相. 日本発達心理学会第20回大会発表論文集, 132. 日本女子大学, 東京.
- (2009). Can children solve Bayesian problems? The role of natural frequency [Abstract]. Poster session presented at the American Psychological Association 117th annual convention (Division 7), Toronto, Canada. (http://forms.apa.org/convention/files/attachment71117.pdf), 4pages.
- (2009). How do people estimate conditional probability of absolute certainty? [Abstract]. Poster session presented at the American Psychological Association 117th annual convention (Division 3), Toronto, Canada. (http://forms.apa.org/convention/files/attachment71119.pdf), 4pages.
- (2009). Developmental analysis on the gambler’s fallacy [Abstract]. The 13th International Conference on Social Dilemmas, 10, Kyoto, Japan.
- (2009). 全事象確率(P=1)の理解に関する発達的研究. 日本心理学会第73回大会発表論文集, 922. 立命館大学, 京都.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2009). 認知的浮動による条件錯誤の説明. 日本心理学会第73回大会発表論文集, 958. 立命館大学, 京都.
- (2009). 「起こり得ない事象」の確率量化に関する発達的研究. 日本教育心理学会第51回総会発表論文集, 304. 静岡大学, 静岡.
- 寺尾 敦・伊藤朋子. (2009). 「ベイズ型くじびき課題」における推論様式の分析−学習にともなう変化−. 日本教育心理学会第51回総会発表論文集, 660. 静岡大学, 静岡.
- (2010). ベイズ型推論課題の難しさ―主題化された課題を用いた検討―. 日本発達心理学会第21回大会発表論文集. 関西エリア連合, 101. 神戸国際会議場, 兵庫.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2010). 連言否定型推論における様相未分化. 日本発達心理学会第21回大会発表論文集, 96. 神戸国際会議場, 兵庫.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2010). 認知的浮動による全面的連言錯誤の説明. 日本心理学会第74回大会発表論文集, 895. 大阪大学, 大阪.
- (2011). 連言確率はどのようなときに混同されやすいか―「2段階くじびき課題」と「医学診断課題」を用いた発達的分析―. 日本発達心理学会第22回大会発表論文集, 430. 東京学芸大学, 東京.
- 中垣 啓・伊藤朋子. (2011). Braineの推論スキーマ「(p∨q)→r,p故にr」は早期に獲得されるのか. 日本発達心理学会第22回大会発表論文集, 133. 東京学芸大学, 東京.
学会発表(自主シンポジウム)
- (企画・司会)永盛善博,(話題提供)伊藤朋子・大浦賢治・柿原直美・阪脇孝子. (2010). 教職課程で発達心理学を学ぶのはなぜか?―認知発達の観点から子どもの発達と教育の関係を探る―. 日本教育心理学会第52回総会発表論文集, 210-211. 早稲田大学, 東京.
学会発表(ラウンドテーブル)
- (企画)永盛善博・阪脇孝子,(ファシリテーター)伊藤朋子・大浦賢治・柿原直美・張王路・橋本展子. (2008). 子どもが「本当に」できることは何なのか?−Piagetの「操作」から子どもの有能性を探る−. 日本発達心理学会第19回大会発表論文集, 201. 追手門大学, 大阪.
- (企画)永盛善博,(話題提供者)伊藤朋子・柿原直美・阪脇孝子・永盛善博,橋本展子. (2009). Piagetの認知発達理論を読み解く. 日本発達心理学会第20回大会発表論文集, 76. 日本女子大学, 東京.
- (企画,話題提供者)永盛善博,(話題提供者)伊藤朋子・大浦賢治・柿原直美・阪脇孝子. (2010). Piagetの認知発達理論から子どもの学習のつまずきを考える. 日本発達心理学会第21回大会発表論文集. 日本発達心理学会第21回大会発表論文集, 75. 神戸国際会議場, 兵庫.
- (企画・話題提供者)阪脇孝子,(司会・指定討論者)永盛善博,(話題提供者)伊藤朋子・大浦賢治・柿原直美・田中美希. (2011). 具体から抽象へ, 「今ここ」から可能性へ―Piagetの発達理論から小学校高学年以降の学習の難しさについて考える―. 日本発達心理学会第22回大会発表論文集, 67. 東京学芸大学, 東京.
学会発表(口頭)
- (2006). ベイズ型推論課題における主要な推論様式. 第7回早稲田大学教育学会研究大会. 早稲田大学, 東京.
- (2007). 確率の1次的量化課題・2次的量化課題における推論様式の分析−予防接種問題を用いて−. 第8回早稲田大学教育学会研究大会. 早稲田大学, 東京.
- (2008). 確率の定義に関する発達的研究. 第9回早稲田大学教育学会研究大会. 早稲田大学, 東京.
- (2009). 人は「確率」をどのようにとらえているのか. 第10回早稲田大学教育学会研究大会. 早稲田大学, 東京.
- (2009). ベイズ型推論課題の推論様式に見られる確率量化操作の獲得水準. 日本認知心理学会第7回大会発表論文集, 27. 立教大学, 埼玉.
- (2009). Difficulty in understanding independent events. Paper & poster presented at the 10th APRU Doctoral Students Conference. Kyoto University, Japan. CD-ROM, 5pages. (口頭発表およびポスター発表)
- 早稲田大学大学院教育学研究科 発達心理学研究室 (有志)(伊藤朋子・永盛善博). (2009). 身近な子どもの不思議な世界−子どもたちは世界をどのように捉えているのだろうか?−. サイエンスアゴラ2009セミナー. 産業技術総合研究所臨海副都心センター別館, 東京.
- (2010). 有意味文脈における認知的浮動の出現. 日本認知心理学会第8回大会発表論文集, 33. 西南学院大学, 福岡.
- (2010). 確率事象の独立性の認識の発達. 日本教育心理学会第52回総会発表論文集, 690. 早稲田大学, 東京.
- 寺尾 敦・伊藤朋子. (2010). 3囚人問題はなぜ難しいのか―ベイズの定理学習後の解答分析―. 日本教育心理学会第52回総会発表論文集, 691. 早稲田大学, 東京.
- (2010). Difference in probabilistic judgment processes between children and adults [Full paper]. Oral (paper) session presented at the Asian Conference on the Social Sciences (ACSS) 2010, Osaka, Japan. (ACAH & ACSS Conference Proceedings CD-ROM, 2723-2734.)
- (2010). Development of probabilistic judgment in humans [Abstract]. Oral session presented at the 15th biennial scientific meeting of the International Society for Comparative Psychology (ISCP), Hyogo, Japan. (Program and Abstracts, p.49.)
- (2010). Precondition to good understanding of probability in math classes at junior high school [Full paper]. Oral (paper) session presented at the 5th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME5), Tokyo, Japan. (Proceedings of EARCOME5, 2, 864-871.)
- (2011). サンプルサイズの無視に関する先行研究の概観と解明すべき課題. 第12回早稲田大学教育学会研究大会. 早稲田大学, 東京.
学会分科会報告
- (2005). 第17回認知発達理論分科会. Gigerenzer, G. (2000). 第6章:How to improve Bayesian reasoning without instruction. In G. Gigerenzer (Ed.), Adaptive thinking: Rationality in the real world (pp.92-123). New York: Oxford University Press. 早稲田大学, 東京.
- (2008). 第27回認知発達理論分科会. Mareschal, D., Johnson, M. H., Sirois, S., Spratling, M. W., Thomas, M. S. C., & Westermann, G. (2007). 第1章:How the brain constructs cognition. In Neuroconstructivism: Vol.1(pp3-28). New York: Oxford University Press. 早稲田大学, 東京.
その他
|
 ■出身大学■
■出身大学■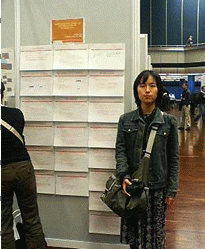 ■出身大学■
■出身大学■