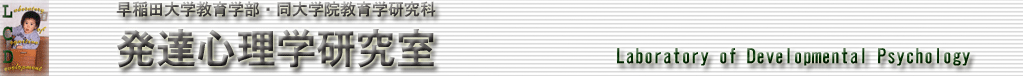指導教員紹介
研究関心
私の研究関心は乳児期から青年期まで、物の永続性課題から形式的操作課題までと
多岐にわたっていて、認知発達の全般に関心があります。とはいえ、なんでも関心が
あるということは、関心について何も語ったことにはならないので、わたしの研究
関心のあり方をいくつかの側面に分けて紹介したいと思います。
実証的研究関心に関してこれまで実証的に研究してきた課題は、論理的推論に関わるもの、確率的推論に 関わるもの、割合や比の観念に関わるもの、組合せ法に関わるもの、計数や演算 順序に関わるもの、数や重さなどの各種保存課題などが中心であったかと思います。 道具使用課題、形あわせ課題、回り道・後戻り課題,物の永続性課題、指差し、 描画、アニミズム、構成遊び等、乳児期あるいはよちよち歩きの子どもたちに 行なうような課題も、自分の子どもについては実施しています。ただこれらは 日常の観察と実験とが入り混じったデータで、これまで一度も発表したことが ないので、今後テーマ別に報告していかなければと思っています。現在振り返ってみれば、論理的推論に関するものが、発表文献としては一番多く なっていると思いますが、初めから論理的推論に特に関心があったわけでは ありません。1980年代、ある有名な認知心理者が子どもでも高度な論理的推論が 可能であると言い出したからです。大人でも難しい論理的課題でも、慣れ親しんだ 文脈を導入し問題解決の意義を明瞭にした課題を提出すれば、子どもでも解けると いうわけです。この考え方の問題点を指摘することは容易だったのですが、もっと 積極的に一見簡単そうに見える論理的推論課題が大人でもなぜ難しいのかを説明 するために、色々な課題を検討する必要に迫られ、結果的に論理的推論に関する 研究に一番時間をとられてしまいました。しかし、時間を費やしただけに、それ なりの成果を上げることができたのではないかと思っています。英米における 論理的推論研究の限界がよく見えるようになってきただけに、海外において発表 すべき研究成果、これから発展させるべき研究課題が山積みの状態です。 研究調査の対象となった子どもたちについていえば、乳児から、幼児、児童、青年 にいたるまで精神発達の全段階にわたっています。ピアジェの認知発達段階論で いえば,感覚運動期、前操作期,具体的操作期,形式的操作期という全時期に わたっています。乳児期については、自分の子どもたちの観察記録と実験に限られ ますが、幼児期以降は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学へ赴いて発達調査 (個別調査、集団調査)を行なってきました。幼稚園児、小学生児童については、 ほとんど個別調査でやってきましたが、大量のデータを取る必要のあるときは例外的に 小学校でも集団調査で実施したことがあります。また中学生以降は、もっぱら集団 調査を実施してきましたが、子どもの反応を詳しく分析する必要のある研究テーマ については高校生、大学生といえども個別調査を実施しています。個別調査は集団 調査に比べて時間的にも、体力的にも大変ですが、私の場合はそれほど苦痛に感じ ません。それは個別調査に行けば、子どもと一対一の関係になり、子どもと向き 合える機会がもてるからです。そういう機会を持てること自体が楽しいのです。 集団調査の場合は、調査のために学校に行ってもクラス単位で行なうわけですから、 子どもと向き合うという感じがなく、データを取りに行ったという印象で終わって しまいます。おそらくこのような印象は私が子ども好きであるということが大いに 関係しているのでしょう。私の最初の調査校であった東京都葛飾区H小学校では、 その日の調査が終わったあと、放課後校庭開放で遊んでいる子どもたちと一緒に 野球やサッカーをして遊んだものです。理屈としては、研究調査をスムーズに 行なうためには子どもたちとのラポートをつける必要があり、そのために子どもの 遊び相手になってあげるということなのでしょうが、本音のところは、子どもたちの 遊び仲間に入れてもらって、自分も子どもたちと遊びたかったのです。子どもの頃 から子ども好きであったといっては笑われそうですが、60歳を過ぎた現在でも、 この気持ちは変わりません。子ども好きであることが発達心理学研究者に必要な 資質の一つであるといっていいのかもしれません。 理論的研究関心に関して実証的研究関心で紹介したように、これまで色々な課題について調査を実施して きましたが、何も行き当たりばったりでやってきたわけではありません。最初の 実証的研究である「組合せ操作の発達的研究」は組合せ操作を実行することと組合せ 操作について知っていることとの関係、言い換えれば、組合せ操作の実行方略とその 概念的理解との関係を見たいという理論的関心の下で行なわれました。このように、 どのような課題を実施するにしても、前もって理論的関心があり、その理論的関心に 応えてくれるような課題を選択、あるいは考案して、実証的研究をやってきたつもりです (ただし、自分の子どもを相手に観察や実験をしていたとき、あるいは、東京都目黒区 F小学校で昼休みを利用して自由に子どもと問答していたようなときは除きます)。 私の理論的研究関心を整理するためには、ピアジェ理論との関係で、お伝えするのが 一番分かりやすいかと思います。1 ピアジェ批判に対する反批判的研究 ピアジェはその理論,方法,課題など、ほとんどあらゆる観点から批判の的になってきました。 とくに、ピアジェ課題として有名な課題については、その結果、その解釈をめぐってたくさんの 批判的研究が行なわれてきました。そこで、ピアジェ理論のパラダイムに立つ研究者としては、 批判的研究に対する反批判が一つの理論的仕事になるかと思います。私の場合、三山問題とか 数の保存課題について、その批判的研究がピアジェ理論に対する的外れの批判になっている ことを示したことがあります。数の保存課題については実証的レベルでも反批判的研究を 行ないました。こうした批判的研究に対する反批判は推移律課題、クラス包含の量化課題、 量の保存課題、測定課題など、ピアジェ課題として有名な課題のいずれについても行なう ことが出来るでしょう。しかしこのような反批判はあまり生産的とは思えません。というのは、 批判的研究の多くはピアジェ理論に対する誤解あるいは不勉強に基づく批判ですから、 一方では良識ある者には(反批判しなくても)いずれ分かってもらえるであろうという 希望的観測があることと、他方ではやるべきもっと重要な研究があるだろうという気持ちが あるからです。とはいえ、英米の発達心理学者あるいは、認知心理学者に定着してしまった ように見えるピアジェ理論に対する誤解については反批判することもそれなり意義がある ことではないかと思っています。すぐ思い浮かぶものとしては物の永続性の獲得基準に 関する議論、表象の発生メカニズムに関する議論、形式的操作の内容依存性をめぐる議論 などがこれに当り、このようなピアジェ理論の根幹に関わるような議論についてはきちんと 反批判していきたいと思っています。 2 ピアジェ理論に基づく通常科学 ピアジェ理論をより深化させるための研究です。一つは領域的な拡大です。ピアジェは 多様な領域にわたって認知発達を研究しましたが、それでも1人の研究者が出来ることには 限界があります。ピアジェが手をつけたが遣り残した課題、全く手をつけていない課題が 広範にあります。メタ認知、心の理論、社会的・経済的認識などはその代表的なものです。 もう一つは領域内での理論的掘り下げです。ピアジェ理論の道具立てを使いながらもピアジェが 明らかにした以上に発達の実相を明らかにすると同時に、その道具立てそのものを洗練して いく研究です。割合の観念の発達的研究はそのような関心のもとに行われたものです。 「組合せ操作の発達的研究」も組合せ操作の実行方略とその概念的理解との関係をもっと 掘り下げたいという理論的関心の下で行なわれたものです。 こういう問題関心と関連して、他の理論的立場から提起された発達の事実をピアジェ 理論とどう関連付けるかという問題もあります。例えば、ゲルマンらは5つの計数原理を 上げ、既に3,4歳で計数原理を知っているとしています。しかし、ゲルマンらの計数原理、 特に基数原理は明らかにピアジェ理論と矛盾しています。この場合、ピアジェ理論の パラダイムに立つ研究者としては、ゲルマンらの計数原理を理論内にどう位置づけるのか、 ゲルマンらの調査結果をどう解釈するのかという理論的問題が提起されるわけです。この 問題については理論的考察だけではなく、実証的レベルでも解決したと思っています。 このように、対立する理論を同化することによっても、理論をより深化させることが 出来るわけです。 ピアジェ理論に基づく通常科学として残されている最大の問題は、言語獲得を如何に 説明するかという問題があります。最大の問題というのは、場合によってはピアジェ 理論のアキレス腱にもなりうるからです。言語と認知とが全く別の経路を辿りながら 発達してくること(ただし、ある時点で両者が合流すること)があきらかになれば、 ピアジェ理論の限界が露呈するでしょう。しかしながら、言語が人間性を規定する 最大の特徴であるといわれながらも、現在でもなお言語遺伝子とか文法遺伝子が 見つかっていないところをみると、言語と認知とは共通の源泉から発生してくることは ほぼ間違いないようです(ここで、言語遺伝子とか文法遺伝子というのは、文法だけ、 あるいはもう少し一般的に、言語だけに関わる遺伝子という意味であって、言語獲得に 遺伝子が関係してないという意味ではありません)。しかし、言語獲得が一般的知能 から如何に可能になるのかを説明する仕事はピアジェ理論のパラダイムに立つ研究者に 課せられている最大のチャレンジであるといえるでしょう。 3 ピアジェ理論を越える研究 理論的研究関心に関する第3の研究はピアジェ理論を越える研究といえるでしょう。 しかし、ピアジェ理論そのものがほとんど理解されていない現状で、「ピアジェ理論を 超える研究」を語ることは時期尚早というものでしょう。それに、ピアジェ理論の 致命的問題点が明らかになっていない現状で、この種の研究を実際にやろうとしても、 言うはやさしく行なうに難しというものです。しかし、いくつかの根本的問題は 考察するに値するのではないかと思っています。 (1)ピアジェ理論にコンピテンス理論はあってもパフォーマンス理論がないこと。 ピアジェ理論は基本的にはコンピテンス理論であって、コンピテンスへの関心は希薄であって、 明確なパフォーマンス理論を持たない。ピアジェのように認識主体epistemic subjectに 関心を持つ場合はそれでもよかったであろう。しかし、心理的主体psychological subjectに 関心を持つ大部分の心理学者にとっては、個々の課題における被験者の実際のパフォーマンスを 説明しようとしないピアジェ理論には大いに不満が残されていた。例えば、形式的操作期に おける認知構造モデルとして16・二項命題操作システムをピアジェは提出している。この モデルは、青年期を児童期から区別する一般的特徴づけとしては有効であっても、この モデルだけでは被験者が現実の課題において示す反応を説明できないのである。実際の パフォーマンスはコンピテンス以外の要因にも多大の影響を受けるからである(教示効果、 文脈効果、内容効果、主題化効果等々)。 ピアジェ理論は基本的にはコンピテンス理論であるという観点は、ピアジェ批判との 関連で特に重要となる。というのは、ピアジェ批判の多くはピアジェ課題において被験者が 発揮するパフォーマンスに向けられているからである。ピアジェが認知システムにおける コンピテンスを問題にしているところで、批判者はそれをパフォーマンスとして受け取り、 ピアジェ理論からは解決できないと想定される時期に高度なパフォーマンスを見出したり、 あるいは逆に、解決できるはずと想定される時期にプリミティブなパフォーマンスしか 見出ださなかったりすることから、ピアジェ批判が展開されるからである。前者は具体的 操作課題に対する批判に多く、後者は形式的操作課題に対する批判に多い。このような 批判を克服していくためには、ピアジェ理論の基本はコンピテンス理論であることを強調 するだけでは不十分であり、ピアジェ理論を包みこんだパフォーマンス理論を構想していく 必要があるだろう。私が博論において最も問題としたことは、コンピテンス理論としての 命題操作システムをパフォーマンス理論として鍛え上げ、それが可能であることを示すことで あった。もっとも、この研究はピアジェ理論をコアアイデアとしているので、ピアジェ理論を 越える研究というより、ピアジェ理論を拡張する研究といった方が相応しいであろう。 (2)認知発達を如何に説明するかという究極の問題 この問題は認知発達研究の究極的課題とでもいうべきものです。おそらく認知発達の研究者 なら誰でもこの問題に関心を持っているであろう。私もまたその例外ではない、というより、 この問題に一番関心を持っているといっていいであろう。とはいえこの問題が最も手に 負えない問題であるということも確かである。液量の保存課題のような、一見単純に見える 課題でさえ、ある時期に非保存判断から保存判断へなぜ移行するのか、この移行と共に保存 認識はなせ規範的認識に変換されるのか、一旦移行が成し遂げられると逆向きの移行が容易 には起こらないのはなぜか、というような認知発達のメカニズムの根幹に関わる問いが次々と 生じてきて、その重荷に押しつぶされそうになります。 ピアジェもこの問題に絶えず立ち返りながら認知発達研究を進めてきました。というより、 ピアジェの長期間の広範囲にわたる認知発達研究はこの問題を解明するためにこそあったと いうことが出来るでしょう。一言で要約するなら、ピアジェは対人的・対物的相互作用に 媒介された動的認知システムの拡大均衡化equilibration majoranteとして認知発達を 説明しようとしました(EEG33, 1973)。この考え方は基本的には誤っていないと思いますが、 まだまだ現象記述の水準を大きく超えてはおらず、質的説明にとどまっています。しかし、 考えてみれば、ピアジェの生きた時代は認知システムのような複雑な系を説明するための 道具立てが極めて乏しかったので、それもやむをえなかったかと思います。1980年でなく なったピアジェに比べ、われわれの方がこの問題を考える上ではるかに有利な立場にある といえるでしょう。イリヤ・プリゴジンの熱力学的非平衡系における散逸構造論、マレー・ ゲルマンの生命情報処理モデルとしての複雑適応系、スチュアート・カウフマンの生命 進化における自己組織化原理など、複雑系における創発(emergence)を説明するための、 したがって認知発達を説明する上で道具立てになりそうな理論、モデルがいろいろと提出 されています。ピアジェ自身晩年にプリゴジンの散逸構造論に注目していたし、プリゴジンも また散逸構造論の具体的モデルをピアジェの認知発達理論に見ていました。また、カウフマンの 自己組織化原理も生命進化を説明するためには自然淘汰に加えて自己組織化原理を必要とする というものです。ピアジェは突然変異と自然淘汰だけでは生命進化を説明できないこと、 認知発達を説明するためには自己組織化(ピアジェはもっぱら均衡化とか自己調整と表現して いました)要因に訴える必要のあることをつとに唱えていたわけですから、直観的にしろ カウフマンの研究より何十年も早く自己組織化原理を洞察していたことになります。こう 考えてくると、「ピアジェ理論を越える研究」として議論してきたにもかかわらず、複雑系 科学の発展はピアジェ理論を越えるどころかピアジェを再び見出す研究になりそうです。 これほどピアジェ理論は懐が深いわけですから、ピアジェ理論を越える研究をしようする よりも、まずこのパラダイムでどこまで行けるかを試す方が生産的だということでしょう。 とはいえ、複雑系科学を認知発達に適用する研究はピアジェ理論を精緻化することには 大いに寄与するでしょう。私も認知発達研究に携わっている限り、この問題に関わって いきたいと思っています。皆さんの中に私と同じような研究関心をもたれる方がいましたら、 是非声をかけてください。一緒に共同研究できる可能性を探りたいと思います。 |
早稲田大学教育学部
早稲田大学大学院教育学研究科 中垣研究室
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1
TEL:03-5286-1598 E-mail:nakagaki@waseda.jp
*メール送信時は@を半角にしてください。
All rights reserved. (c)2009.